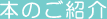YOGAクラスの過去のテーマとヨガのポーズをご紹介します。
 |
ボディスキャン 後編(肩から上) (2025年4月) ボディスキャンでは、何もしない。どこも動かさない。ただ呼吸とともにゆっくり注意を向けていくことで、自分の身体の部分と部分がつながり、部分は全体とつながり、統合され、しかも一瞬も滞ることのない、いわば流れとしての人体、今この瞬間瞬間に生きている自分という存在を感じられます。 [詳細] |
 |
ボディスキャン 前編(つま先から肩まで) (2025年3月) 自分のからだが今この瞬間にどう感じているのか、感じているままに受け止めるボディスキャンは、注意集中の対象を移動させていきます。その前の部分で感じたことをいったん忘れて、次に今この瞬間に注意集中する部分をテイスティングします。 [詳細] |
 |
コブラのポーズ (2025年2月) <コブラのポーズ>はコツが掴めてくると、しなやかさと力強さ、そして癒しを感じられるポーズです。寒さで丸まりがちな背中を優美に伸ばせます。 [詳細] |
 |
苦手なモノ・コトとの付き合いマインドフルネス (2025年1月) マインドフルネスとは〝1人で行うカウンセリング〟と言ってもいいでしょう。 〝心の筋力トレーニング〟という指導者もいます。 自分に備わっている本来の力を肯定し、信頼していく営みには、心の表層を雑多に表れる思いや考えの流れに気づき、しかし、そのどれにも飲み込まれず(飲み込まれている瞬間に気づき)、自分に戻れるということです。 [詳細] |
 |
マインドフルネスの実習2 (2024年12月) 呼吸に注意を向けて、そのプロセスを味わうようにしていくと、不思議なことに呼吸が落ち着いてきます。肝心なのは、呼吸を落ち着かせるために行うのではないこと。ただ呼吸に注意を向けていくうちに、呼吸が静かに深くなってくることが多いのです。 [詳細] |
 |
マインドフルネスの実習 (2024年11月) マインドフルネスとは、今この瞬間に起きていることをしっかりていねいに味わうこと。今この瞬間に心の働きをとどめておくには、少しトレーニングが必要です。〝考えない訓練〟といったらいいのかな。マインドフルネスを〝心の筋力トレーニング〟にたとえるのも、ほんの少しの練習が必要だからです。 [詳細] |
 |
椅子を使った背中立ちのポーズ (2024年10月) 気楽に胃腸の体位を逆転させ、腹式のゆったりした呼吸をすることで、お腹が温かくなるのがわかります。暑い暑いと思っていても、腹部は意外と冷えています。 疲れやだるさを感じたら<椅子を使った背中立ちのポーズ>をぜひ試してください。 [詳細] |
 |
なんちゃってハトのポーズ (2024年9月) 前月の<ハトのポーズ>さて自分でやってみて「あれっ?」「あれあれ~?」と困惑した人も多いのでは。 なので今回改めて<初級(なんちゃって)ハトのポーズ>をとりあげます。 [詳細] |
 |
ハトのポーズ (2024年8月) 体側を伸ばし、肩甲骨周りの筋肉をほぐし、股関節周りの柔軟性を高めて大腿部のオモテ筋肉をほぐす、とても気持ちのいいポーズです。 しかし、完成度を求めるときついので、<な~んちゃってハトのポーズ>くらいの気持ちで始めましょう。 [詳細] |
 |
T字のポーズ (2024年7月) 今月はバランス力を高める<T字のポーズ>を紹介します。難易度が高いので、くれぐれも適当にやってください。 流れが大事なのでおぼえているポーズも組み合わせて、くつろぐことも入れて、15分くらいゆったりした流れで行えれば「よし!」です。好きなストレッチを入れてもOKですよ。 [詳細] |
 |
半月のポーズ パート2 (2024年6月) 先月ご紹介した<半月のポーズ>とからだの使い方の基本は同じです。まず骨盤(仙骨を意識する)を前方に移動、それに伴って両腕と上体を後方に傾けていきます。反らそうではなくて、手を上へ上へと伸ばしていくと意識することで、無理なくできます。 [詳細] |
 |
半月のポーズ (2024年5月) 今月紹介するのは、左右の体側と肩腕を伸びやかにしなやかに伸ばしていくポーズです。骨盤が腕とは反対方向に連動して動くのがポイント。まず、壁を背にして行ってみることをお勧めします。 [詳細] |
 |
ウサギのポーズ (2024年4月) 先月、先々月と2回にわたって紹介した<ラクダのポーズ>と対照形のポーズです。通常、<ラクダのポーズ>と<ウサギのポーズ>を交互に行います。<ラクダのポーズ>が苦手な人も<ウサギのポーズ>を行った後に行うと、気持ち良くできます。 [詳細] |
 |
ラクダのポーズ (2024年3月) 前月は片側ずつ行いましたが、その続きで今回は両手をかかとに置き、胸を開きます。 何の気なしにこのポーズをとると、腰が反りすぎてしまい(お腹が緩んでいます)、腰を痛めます。また首を後ろに脱力するので、不安に感じる人も中にはいます。先月の<片ラクダのポーズ〉が気持ちよく行えるのなら、それで十分です。腰をそらすのではなくて、肛門を閉じ、お腹を引き締めて行うのがキモです。 [詳細] |
 |
片ラクダのポーズ (2024年2月) 年の初めは大きく伸びをするように身体を動かして、免疫力を高めようと提案したい。 胸が気持ちよく開かれる<ラクダのポーズ>、これから2回にわたり紹介していきます。今月は左右片側ずつの<片ラクダのポーズ>です。 [詳細] |
 |
背中立ちのポーズ (2024年1月) 今月紹介する「背中立ちのポーズ」、お腹を楽にしてくれます。腸には脳以上の数の神経細胞があり、気分を左右する物質を放出しているそうです。腸活の1つにぜひ加えてほしい。 胃腸をリラックスさせるポーズです。 [詳細] |